会社の先輩の訃報に接し、初めて香典を準備することになったものの、「何から手をつければ…」と不安な気持ちでいらっしゃいませんか?
ご安心ください。ポイントさえ押さえれば、香典の準備は決して難しくありません。
この記事では、あなたの不安を安心に変える「一番やさしい5ステップ・チェックリスト」をご用意しました。この記事を読み終える頃には、あなたは迷いなく準備を終え、自信を持って先輩のもとへ向かえるようになっています。
「常識ないと思われたら…」初めての香典、その不安の正体
初めて香典を準備されるのですね。お察しいたします。きっと「失礼のないように」と、たくさんの情報を調べて、かえって混乱されている頃ではないでしょうか。
大丈夫ですよ。一番大切なのは、故人を悼み、ご遺族をいたわる、そのお気持ちです。これから、その大切な気持ちがきちんと伝わるよう、私が隣で一つひとつお手伝いしますね。
私が葬儀の現場で、みなみさんのような若い方から本当によく受ける質問があります。それは「相手の宗派が分からないのですが、どうすれば?」というものです。この質問の裏には、「良かれと思ったことが、かえって失礼になったらどうしよう」という深い不安が隠れています。
香典のマナーとは、相手を不快にさせないための「思いやり」を形にしたもの。だからこそ、基本を知っておくことが、あなたの自信と安心に繋がるのです。
もう迷わない!香典準備の全工程5ステップ・チェックリスト
ここからは、この記事の核となる、香典準備の具体的な手順を5つのステップに分けて解説します。この通りに進めれば、誰でも間違いなく準備を終えられますので、安心してくださいね。
ステップ1:【用意するもの】香典袋と薄墨ペンを準備する
まず、香典袋と薄墨(うすずみ)の筆ペンを用意しましょう。これらはコンビニエンスストアや文房具店、スーパーマーケットなどで手に入ります。
香典袋には様々な種類がありますが、包む金額が5,000円〜10,000円程度の場合、白黒の水引(みずひき)が印刷されたシンプルなデザインのものを選べば間違いありません。
✍️ 専門家の経験からの一言アドバイス
【結論】: 筆記具は、ボールペンや万年筆ではなく、必ず「薄墨の筆ペン」を選んでください。
なぜなら、薄墨には「悲しみの涙で墨が薄まってしまいました」という弔意を表現する意味が込められているからです。この点を押さえるだけで、あなたの深いお悔やみの気持ちがより一層伝わります。
ステップ2:【外袋の書き方】「御霊前」と自分の名前を書く
香典袋の準備ができたら、次にその外面に表書き(うわがき)を書きます。
水引の上段中央に、「御霊前(ごれいぜん)」と書くのが最も安全な選択です。「御霊前」という表書きは、仏教の多くの宗派や神道、キリスト教など、幅広い宗教で使えるためです。
そして、水引の下段中央に、ご自身のフルネームを「御霊前」の文字より少し小さめに書きます。
ステップ3:【中袋の書き方】金額と住所・氏名を書く
多くの香典袋には、お札を直接入れるための中袋(なかぶくろ)がついています。この中袋への記入は、ご遺族が後で整理する際に非常に重要になります。
- 表面: 中央に、包んだ金額を縦書きで記入します。数字は「壱」「弐」「参」のような大字(だいじ)を使うのが正式ですが、「一」「二」「三」でも問題ありません。例えば5,000円なら「金 伍阡圓」または「金 五千円」と書きます。
- 裏面: 左下に、ご自身の郵便番号、住所、氏名を記入します。
ステップ4:【お金の入れ方】旧札を正しい向きで入れる
中袋にお札を入れます。この際、旧札(きゅうさつ)、つまり使い古したお札を入れるのがマナーです。新札は「不幸を予期してあらかじめ準備していた」という印象を与えかねないため避けます。
お札を入れる向きは、全てのお札の肖像画(顔)が描かれている面を、中袋の裏側(下側)に向けて揃えて入れます。「顔を伏せる」ことで、悲しみを表現すると言われています。
✍️ 専門家の経験からの一言アドバイス
【結論】: もし手元に新札しかない場合でも、慌てずに一度くっきりと折り目を付けてから入れれば問題ありません。
なぜなら、大切なのは「急な訃報に際し、慌てて用意しました」という気持ちを示すことだからです。折り目を一つ付けるだけでその意図が伝わりますので、わざわざ旧札を探し回る必要はありませんよ。
ステップ5:【渡し方の準備】袱紗(ふくさ)に包む
全ての準備が整った香典袋は、袱紗(ふくさ)という布に包んで持参するのが正式なマナーです。袱紗は香典袋が汚れたり、水引が崩れたりするのを防ぐ役割があります。
弔事(ちょうじ)用の袱紗は、紫や紺、深緑、グレーといった寒色系の色を選びます。紫色の袱紗は慶事(けいじ)・弔事どちらにも使えるため、一つ持っておくと便利です。
【金額・書き方】関係性別・状況別の完全マニュアル
「私の場合は、具体的にいくら包めばいいの?」という疑問にお答えします。包むべき香典の金額は、故人との関係性やご自身の年齢によって変わります。
会社の先輩のお父様が亡くなられた今回のようなケースでは、高すぎる金額はかえってご遺族に香典返しなどで気を遣わせてしまうため、相場を知っておくことが大切です。
【関係性・年代別】香典金額の相場一覧
| 故人との関係 | あなたの年代 | 金額の相場 |
|---|---|---|
| 勤務先の上司・同僚・部下 | 20代 | 3,000円 ~ 10,000円 |
| 30代 | 5,000円 ~ 10,000円 | |
| 勤務先の人の”家族” | 20代 | 3,000円 ~ 5,000円 |
| 30代 | 5,000円 ~ 10,000円 | |
| 友人・知人 | 20代 | 3,000円 ~ 5,000円 |
| 30代 | 5,000円 ~ 10,000円 | |
| 祖父母 | 20代 | 10,000円 |
| 30代 | 10,000円 ~ 30,000円 | |
| 親 | 20代 | 30,000円 ~ 100,000円 |
| 30代 | 5,0000円 ~ 100,000円 |
この表からわかるように、20代のあなたが会社の先輩のご家族へお渡しする場合、5,000円が一つの適切で丁寧な目安となります。
これってどうなの?香典の「最後の疑問」に答えるQ&A
Q. 会社の同僚と連名の場合はどう書く?
A. 3名までの連名であれば、水引の下段中央に、目上の方の名前を右から順に書きます。4名以上になる場合は、代表者の氏名を中央に書き、その左下に「外一同(他一同)」と書き添え、全員の氏名・住所・金額を記した別紙を中袋に同封します。
Q. お通夜と告別式、両方参列する場合は?
A. 香典は、どちらか一方に参列する際にお渡しすれば問題ありません。一般的にお通夜に持参する方が多いです。両方に参列する場合でも、香典を二度渡すのは「不幸が重なる」ことを連想させるため、避けるべきです。
Q. どうしても薄墨の筆ペンが見つからない場合は?
A. 万が一、薄墨の筆ペンが手に入らない場合は、通常の黒い筆ペンでも構いません。その際は、心を込めて丁寧に書くことを一番に心がけてください。ボールペンや鉛筆で書くことだけは避けましょう。
まとめ:大切なのは、あなたの「気持ち」です
長い時間、お疲れ様でした。最後に、これだけは覚えておいてください。
- 金額は「5,000円」が丁寧な目安。
- 表書きは「御霊前」と書けば最も安心。
- 筆記具は「薄墨」で、悲しみの気持ちを表す。
この3つの基本が、あなたの「先輩を悼む温かい心」を伝えるための大切な土台となります。
完璧なマナーよりも、故人を思い、ご遺族をいたわるあなたの気持ちが何よりも大切です。自信を持って、お気持ちを伝えてきてくださいね。
さあ、まずはコンビニエンスストアか文房具店で「香典袋」と「薄墨の筆ペン」を手に入れるところから、始めてみましょう。
[監修者情報]
この記事の監修者
山田 太郎 / 株式会社セレモニア 代表取締役
葬儀業界歴25年。これまで5,000件以上の葬儀を執り行い、ご遺族に寄り添った温かいお見送りを信条とする。業界の健全な発展のため、若手育成と情報発信にも力を入れている。
[参考文献リスト]
参考文献
- 「香典の金額相場・書き方・渡し方など葬儀マナーを徹底解説」 – いい葬儀, (https://www.e-sogi.com/guide/17589/)
- 「香典に5000円を包むとき、香典袋の書き方やマナーを解説」 – RINGBELL MAGAZINE, (https://www.ringbell.co.jp/ringbell/contents/kouden/9217)
- 「【宗教別】香典の書き方を表書き・名前・金額・中袋に分け徹底解説」 – ほしのなる木, (https://hoshinonaruki.jp/houyou/863/)

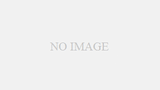
コメント