お父様が肺炎と診断され、ご自宅での看病、本当にご不安ですよね。「自分のケアは正しいだろうか」と心配になるお気持ち、よく分かります。
ご安心ください。実は、ご家族が気をつけるべき「絶対にしてはいけないこと」は、いくつかの重要なポイントに絞られます。
この記事では、呼吸器専門医である私が、なぜそれをしてはいけないのか、その「理由」まで詳しく解説します。
最後まで読めば、お父様の回復のために本当に大切なことが分かり、自信を持ってケアできるようになります。
なぜ高齢者の肺炎は特に注意が必要?ご家族が知るべき3つの理由
多くのご家族が「なぜ、うちの親が肺炎に?」と驚かれます。高齢者の肺炎は、若い人の肺炎とは異なり、ご家族が特に注意すべき3つの理由があります。これから解説する「してはいけないこと」の重要性を理解するために、まずはお父様の体で何が起こりやすいのかを知っておきましょう。
- 典型的な症状が出にくい
若い人なら高熱や激しい咳が出る場面でも、高齢者の場合は「なんとなく元気がない」「食欲がない」「少しぼーっとしている」といった、はっきりしない症状で始まることが少なくありません。このため発見が遅れやすく、ご家族の「いつもと違う」という気づきが非常に重要になります。 - 「誤嚥(ごえん)」しやすくなっている
高齢になると、飲み込む力(嚥下機能)が自然と衰えてきます。嚥下機能の低下は、食べ物や唾液が誤って気管に入ってしまう「誤嚥」を引き起こし、それが肺の炎症につながる「誤嚥性肺炎」の直接的な原因となります。高齢者の肺炎の多くが、この誤嚥性肺炎です。 - 重症化しやすく、命に関わる
もともと心臓や腎臓などに持病を抱えている方が多い上に、肺炎そのものが体力を大きく消耗させるため、重症化しやすい傾向があります。実際に、日本の統計では肺炎で亡くなる方の95%以上が65歳以上の高齢者であり、肺炎は高齢者にとって命に関わる病気なのです。
【医師が断言】肺炎の悪化を防ぐ「絶対にしてはいけないこと」リスト
それでは、お父様の肺炎を悪化させないために、ご家族が「絶対にしてはいけないこと」を具体的にお話しします。一つひとつの理由を理解することが、自信を持ったケアにつながります。
1. 自己判断で抗菌薬(抗生物質)をやめる
症状が少し良くなったように見えても、医師から処方された抗菌薬を自己判断で中断することは、絶対にしてはいけません。
その理由は、中途半端な服薬が、薬の効かない強力な細菌「耐性菌」を生み出す原因になるからです。肺炎の原因菌が完全にいなくならないうちに薬をやめると、生き残った菌が薬への抵抗力を持ち、次に同じ薬を使っても効かなくなってしまいます。処方された抗菌薬は、必ず最後まで飲み切るようにしてください。
✍️ 専門家の経験からの一言アドバイス
【結論】: 「症状が消えた=治った」ではない、と心に刻んでください。
なぜなら、この点は多くのご家族が陥りがちな最大の失敗ポイントだからです。熱が下がったり、咳が減ったりすると安心してしまうお気持ちは分かりますが、それは抗菌薬が効いて菌の活動を抑えているだけです。ここで油断せず、医師の指示通りに服薬を続けることが、再発を防ぐ最も確実な方法です。
2. 食事で無理強いをする・誤嚥しやすいものを与える
「体力をつけてほしい」という思いから、無理に食事をさせようとすることも避けるべきです。特に、飲み込む力が落ちているお父様にとって、食事は誤嚥性肺炎の直接的なリスクになります。
サラサラしたお茶や汁物、パサパサしたパンやクッキー、むせやすい粉薬などは特に注意が必要です。食事の際は、体をしっかり起こし、少量ずつ、ゆっくりと時間をかけることを心がけてください。
3. 水分補給を怠る
肺炎の時は、発熱や呼吸によって体から水分が失われやすく、脱水症状に陥りがちです。脱水症状は、痰の粘り気を強くして、肺から排出しにくくさせるため、肺炎の悪化を招く増悪因子となります。
のどが渇いていなくても、こまめに水分を摂るよう促しましょう。一度にたくさん飲ませるのではなく、スプーンやストローを使い、少量ずつ頻繁に与えるのがポイントです。
4. 一日中、完全に寝かせきりにする
安静はもちろん重要ですが、過度に体を動かさないでいると、肺の奥に痰がたまりやすくなり、かえって肺炎を悪化させることがあります。
医師の許可があれば、ベッドの頭を少し起こして座る時間を設けたり、可能であれば部屋の中を少し歩いたりすることも、痰を出す助けになります。どの程度の活動が適切か、必ずかかりつけ医に確認しましょう。
5. 「いつもと違う」サインを見逃す
前述の通り、高齢者の肺炎は症状が分かりにくいのが特徴です。「呼吸がいつもより速い・浅い」「唇の色が青白い」「呼びかけへの反応が鈍い」「つじつまの合わないことを言う」といった変化は、重症化のサインかもしれません。
これらの「いつもと違う」様子に気づいたら、「歳のせいかな」と様子を見過ぎず、すぐに医療機関へ連絡してください。
では、どうすれば?ご自宅でできる具体的なケアのポイント
「してはいけないこと」が分かった上で、次にご自宅での自宅療養で積極的に行ってほしい具体的なケアのポイントを4つご紹介します。
- 食事の工夫
無理強いは禁物ですが、栄養を摂ることは回復に不可欠です。飲み込みやすいように、食事にとろみをつけたり、ゼリー状の栄養補助食品を活用したりするのがおすすめです。 - 上手な水分補給
水やお茶でむせてしまう場合は、市販の経口補水液や、とろみをつけた飲み物を利用しましょう。イオン飲料も吸収が良く、脱水予防に効果的です。 - 口腔ケアの徹底
自宅療養における誤嚥性肺炎の予防には、お口の中を清潔に保つ口腔ケアが極めて重要な要素です。口の中の細菌が唾液と一緒に肺へ流れ込むのを防ぐため、毎食後や就寝前に、歯ブラシやスポンジブラシで丁寧に清掃してあげてください。 - 環境の整備
部屋の空気が乾燥すると、喉や気管の粘膜が傷つきやすくなります。加湿器を使って、湿度を50〜60%に保つようにしましょう。また、定期的な換気も大切です。
| 肺炎の時の食事の注意点(OK例とNG例) | おすすめの食事(OK例) | 避けるべき食事(NG例) | |
|---|---|---|---|
| 主食 | 全粥、やわらかく煮たうどん | パサパサしたパン、お寿司 | |
| おかず | 卵豆腐、茶碗蒸し、白身魚の煮付け | 硬い肉、繊維の多い野菜(ごぼうなど) | |
| 飲み物 | とろみをつけたお茶、経口補水液、野菜スープ | 酸味の強いジュース、炭酸飲料、牛乳 | |
| その他 | 栄養補助ゼリー、プリン、ヨーグルト | 餅、ナッツ類、ポテトチップス |
よくある質問(FAQ)
最後に、ご家族からよくいただく質問にお答えします。
Q. 肺炎は家族にうつりますか?
A. 肺炎の原因となる菌の種類によりますが、一般的な高齢者の誤嚥性肺炎の原因菌は、もともとご自身の口の中にいる常在菌であることがほとんどです。そのため、健康なご家族にうつる心配は基本的にありません。ただし、インフルエンザやコロナウイルスなどが原因のウイルス性肺炎の場合は感染力がありますので、手洗いやマスク着用などの基本的な感染対策は徹底しましょう。
Q. お風呂にはいつから入れますか?
A. 入浴は体力をかなり消耗します。熱が下がり、呼吸の状態が安定して、医師の許可が出てからにしましょう。それまでは、体を温かいタオルで拭いてあげる(清拭)だけでも、さっぱりして気持ちが良いものです。
Q. どんな症状が出たら、すぐに病院へ連絡すべきですか?
A. 「呼吸が明らかに苦しそう」「肩で息をしている」「唇や爪の色が紫色になっている」「呼びかけにほとんど反応しない」といった症状が見られた場合は、ためらわずに救急車を呼ぶか、すぐにかかりつけ医に連絡してください。
まとめ:ご家族の観察が、お父様を守る一番の力です
高齢のお父様の肺炎ケアで最も大切なのは、「自己判断しないこと」そして「日々の小さな変化に気づくこと」です。本日お伝えした「5つの禁止事項」を、ぜひ心に留めておいてください。
- 自己判断で抗菌薬をやめない
- 食事で無理強いをしない
- 水分補給を怠らない
- 一日中寝かせきりにしない
- 「いつもと違う」サインを見逃さない
ご家族のサポートが、お父様にとって何よりの力になります。不安でいっぱいだと思いますが、一人で抱え込まず、私たち専門家を頼ってくださいね。
もし少しでも不安なことや、判断に迷うことがあれば、ためらわずに、かかりつけの医師や訪問看護師に相談してください。
[参考文献リスト]
- 厚生労働省 e-ヘルスネット「肺炎」
- 日本呼吸器学会「成人肺炎診療ガイドライン」
- 一般社団法人 日本老年医学会「高齢者肺炎」に関する情報ページ

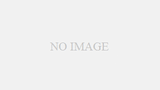
コメント